浦川登久恵
朝鮮最初の女性西洋画家である「羅蕙錫(ナ・ヘソク)」。
文筆の才もあった彼女は若くして時代の脚光を浴びたが、後半生は経済的苦境に苦しみ、世間との軋轢を抱え、好奇の目で語られる存在でもあった。

1 日本への留学と若き日の決意
羅蕙錫は1896年、ソウルから35キロほど南に位置する水原(スウォン)の裕福な家に生まれた。優秀な成績で女学校を卒業した彼女は、1913年、東京の女子美術学校(現・女子美術大学)へ留学、西洋画を専攻し、磯野吉雄や岡田三郎助、足助恒らの指導を受け、絵画の基礎を学ぶ。朝鮮において、女性として、留学をしてまで高等教育を受けることのできた最初の世代である彼女は、時代の先駆者たらん、という意欲に燃えていた。快活で、はっきりとものを言い、男子学生とも気兼ねなく話をすることができるような性格の女性だったという。在学中に、よい縁談があるから学業をやめて戻ってこい、と父に厳命されたときも、己の力を生かすように生きてみたい、と父に逆らい、いったん休学して学費を稼いで復学し1918年に美術学校を卒業するのである。卒業の時期に、留学生仲間の雑誌『女性界』に載った彼女の小説「キョンヒ」には、そうした彼女と等身大の主人公・キョンヒの揺れる心情が巧みな構成で描かれている。父親に対して「今は女でもなんだってできる時代なんです」と大見得を切ったものの、やっぱり自分が間違っているのか、たいした知識もない自分のような人間に何かを成し遂げることなどできるだろうか、と逡巡し苦しむキョンヒの姿は、実在の羅蕙錫の姿と重なっていたはずである。
2.副領事の妻として、母として、画家として
朝鮮に帰った翌年の1919年、3・1独立運動が朝鮮全土に広まる中、羅蕙錫も留学生仲間たちと婦人団体を立ち上げ独立運動を展開しようと計画していたところを逮捕され、証拠不十分で不起訴となるまで5か月間拘束される。
翌年、羅蕙錫はかねてから求婚されていた金雨英(キム・ウヨン)と結婚する。羅蕙錫24歳、金雨英は京都大学法学部を出た弁護士で、羅蕙錫より10歳年上だった。熱心なクリスチャンである彼は吉野作造や末広重雄を自分の恩師として名を挙げているが、吉野も末広も、日本の朝鮮統治のあり方に疑問を投げかけた知識人だった。熱く政治を語り愛を語る金雨英に、羅蕙錫もしだいに惹かれていったらしい。新婚当時の彼らの仲睦まじい様子は、画家仲間で先輩である石井伯亭も目撃し記録している。結婚の翌年3月、羅蕙錫はソウルで個展を開き、二日間で5千人の観客を集めた。3・1運動後のいわゆる「文化政治」時代の到来に合わせたように、羅蕙錫は若くして時代の脚光を浴びる存在となっていた。
1921年9月、金雨英は日本の在外領事館である安東(現在の中華人民共和国丹東市)の副領事に特別任命され、羅蕙錫も4月に生まれたばかりの長女を抱いて移住した。日本当局による朝鮮人懐柔策の一環ではあったが、金雨英は現地の朝鮮人の教育や金融問題に取り組み、羅蕙錫も夫とともに夜学の立ち上げなどに尽力する。そしてまた、彼ら夫婦は副領事夫妻という立場を利用して武装独立運動の手助けをもしている。安東は朝鮮半島から中国へ抜ける際の交通の要衝だったが、夫婦はそこを行き来する活動家の移動を手助けし、時に武器を預かるという、かなり危険な行動をとった。「民族の独立」という大命題が、そこにはあった。
だが、彼女がもっとも力を注いだのは何と言っても「絵画」である。おりしも、ちょうどこの時期、文化政治の一環として、朝鮮美術展覧会が始まった。彼女は1922年の第1回から参加し、6年連続で入選、特選などの成果を残している。鮮展の出品資格は朝鮮人のほか、朝鮮に6カ月以上滞在している日本人にも与えられ、審査委員には多くの著名な日本人画家が交代で任命された。第1回のときには、西洋画で61人が入選しているが、そのうち朝鮮人は羅蕙錫を含めて3人だけで、女性は彼女だけだった。いかに彼女の存在が突出していたかがわかる。
安東へ行ってからさらに2児を授かり三人の幼子の母となった彼女は時間の捻出だけでもたいへんだった。寝る間を惜しんで描き続けたが、やがて自分の絵について煩悶生じる。自分の絵は「形態と色彩と光線にのみ重きをおいて」「芸術的気分が薄弱」で「精神的進歩がない」と。実際、第6回の鮮展出品作は無鑑査入選だったが、評判は概してよくなかった。そんなとき、行き詰まりを感じていた彼女に、何とも幸運な話がころがりこむ。
3.欧米視察
夫・金雨英が1927年、副領事勤務を解かれ、「僻地勤務を勤めたものに与えられる慰労旅行」としてヨーロッパ、アメリカ行きが決まった。彼ら夫婦は、三人の幼子を夫の実家に預け、なんと1年8カ月もの長期海外視察に出るのである。羅蕙錫は「私はフランスで絵の勉強をしたい」と知人宛ての手紙で宣言している。
さて、シベリア鉄道でヨーロッパに入り、そこから大西洋を渡りアメリカに行き、アメリカ大陸を横断して太平洋を渡って帰国する、という文字通り世界一周の22か国もの国々を巡った中で、羅蕙錫がいちばん長く滞在していたのは何と言ってもパリである。彼女はそこで一人で一般家庭に寄宿しながらアカデミー・ランソンに通って絵を学ぶ、という機会を得ることができた。当時ランソンで教えていたロジェ=ビシエールには、板倉鼎ら日本人画家も多く師事している。羅蕙錫は、立体派、野獣派など当時のフランス画壇で注目されているものは何かを探り、自分の方向を定めようとしていたのだろう。だが、彼女のパリ滞在はのべ約8カ月。時間が足りない、という思いは強く残らざるを得なかった。 のちに彼女は、「誰の指導をいちばん受けましたか?」という記者の問いに朝鮮美展の審査員も務めた小林万吾の名を挙げているが、同時に、「その影響を私の絵から探すのは難しい」という趣旨の説明を加えている(1933年のインタビュー)。彼女にとって、決定的な影響を受けた画家はいなかったといえるのではないだろうか。 さて、羅蕙錫はこのパリで、崔麟(チェ・リン)と運命的な出会いをもってしまう。崔麟は羅蕙錫より18歳年上でこのとき49歳。天道教の幹部であり、1919年の「3・1独立宣言」にも民族代表の一人として名を連ねた、当時の朝鮮における代表的な知識人の一人である。崔麟は、自治制をめぐって総督府側とも連絡をとりつつ、この時期ヨーロッパ中心に展開されていた「弱小民族」運動の視察もかねて、アメリカ経由でヨーロッパにやって来ていた。金雨英がドイツに行き、パリに残った羅蕙錫は、崔麟と通訳も交えて三人で行動することが多くなり、二人の仲は急接近し、ホテルで一夜を共にするほどの仲になった。開放的なパリの雰囲気の中で抑制もきかず深い関係に落ちた二人だったが、互いの家庭を壊してまで、という気持ちは双方ともになく、二人の関係は3カ月ほどで終わる。だが、この出会いは、帰国後の彼女の運命を狂わせるものとなった。

4. 離婚 ― 告発と訴訟
崔麟との出会いと別れから約1年3か月後の1929年3月、羅蕙錫夫婦は朝鮮に戻る。彼女は身重の身で、 6月に4人目の子どもが生まれた。豪華客船で帰ってきた彼女に待ち受けていたのは、夫の実家での窮屈な暮らしと、生活難だった。夫は官吏の生活に戻らず再び弁護士業を始めると言って、その開業資金作りだけでもたいへんのなに、次から次と親戚が押し寄せてきたのである。乳飲み子を抱えて身動きがとれない彼女は、崔麟に「何か事業ができないだろうか」と手紙を書くが、この手紙が夫の知るところとなり、大激怒を買ってしまう。パリでの噂をいったんは目をつぶることにした金雨英だが、帰国後も連絡をとろうとする妻を、どうしても許せなかったのだろう。彼は羅蕙錫に離婚を宣告し、その後一切の弁明を聞こうとしなかった。羅蕙錫はプライドもかなぐり捨てて離婚に抵抗するが、結局裸同然で婚家を追い出される。四人の子どもも、当然置いて行かねばならなかった。
復縁に一縷の望みをかけていた羅蕙錫は、その後金雨英がすぐに再婚したと知って精神的に大打撃を受けるが、画家として生きて行こう、と自らを奮い立たせるしかなかった。1931年、パリのクリュニー美術館を描いた「庭園」が鮮展で特選となり、日本の帝展でも入選を果たす。このころが画家としての彼女の絶頂期といってもいいかもしれない。彼女は、学費の工面を夫の恩師である吉野作造に頼みに行ったり、関西の篤志家である柳原吉兵衛に絵を売り込んだりして、必死に絵を描き続ける方途を探った。が、不幸は重なってやってきた。翌年、滞在していた家の火事で絵の多くを失ってしまい、その打撃からか手が震える、という症状に見舞われるようになる。さらに奮起して「女子美術学舎」という学校をソウルに開設するが、経営はすぐ行き詰まってしまう。
追い詰められた彼女は、崔麟を相手に貞操蹂躙訴訟をおこした。当時、貞操蹂躙を理由とした金銭要求の訴訟がたびたびおこされていた時代ではあったが、羅蕙錫は、訴訟の動機について「恨みをはらす」「とても薄情なので」という発言をしている。崔麟とのことが原因で離婚に至り、女である自分は家庭も経済的基盤も世間の評判も失ったのに、崔麟は何も失わず相変わらず宗教界の幹部として高い社会的地位を維持しており、何の援助も連絡もくれない。理不尽を感じての行動だったが、あと味はいいものではなかった。裁判は回避され、崔麟の側がいくばくかの金額を支払って終わったが、それから間もない時期に行われたインタビューで彼女はこう答えている。「私の希望はひとつだけ。人間として自由に、そして思う存分芸術の創作に精進してみたいということだけです。先日の事件で世間からたくさん非難されたでしょう?考えてみると、私の過ちでした。笑い話です」。
5. 文筆での闘い、そして仏教の世界へ
訴訟と同時期に、羅蕙錫は離婚に至った顛末を「離婚告白状」として雑誌に発表した。離婚の際、夫の周辺があれこれ口を出し「強くて激しい女の前途がみじめになっていくさまを演劇でも見物するように見てみたい」という様子だったことや、「善良な夫」であった金雨英が「恐ろしい決断性、残酷な唾棄性」を発揮して繰り返し離婚を迫ったことなどを克明に生々しいセリフとともに書き連ねた。羅蕙錫の文筆は、理性的かつ合理的な視点で社会の改良を訴える一方で、ときに「正直」すぎて世間の反発を買うこともしばしばだった。初めて子どもを授かったときも、子どもを、自分の妨げになる、と思ってしまった自分の感情などを率直に語り、母という聖職を何と心得るか、的な批判を受けてしまう。だが、これは彼女が日本に留学した時代の雰囲気、社会風潮の反映である部分が大きい。個性の尊重が叫ばれ、雑誌『青鞜』などで性に関する率直な女同士の議論が繰り広げられていた時代、彼女の感性はそうしたものをしっかりと吸収して自分のものにしていたのである。
崔麟に対する訴訟の後も、保守的な世間に挑戦するかのような文章を発表し続けていたが、やがて彼女は仏教への傾斜を深めていき、修徳寺という寺に身を寄せ、その手前に位置する修徳旅館で主に暮らすようになる。終戦直前の1944年からはソウルの養老院に入るが、寺でも養老院でも、彼女は震える手で絵を描き、画家仲間との交流を楽しみ、文章を綴っていたことが多くの証言から確認されている。養老院からしばしば抜け出して知人を訪ね歩く生活だったが、1948年の冬、この世を去った。52歳だった。
死後、羅蕙錫は主に二つの語られ方をしていた。一つは、貧困のうちに行き倒れて死んだ悲惨な「新女性」として、もうひとつは華麗なる自由恋愛を楽しんだ芸術家として、である。1988年、小説「キョンヒ」が発掘されたことが契機となり、以後、彼女の再発見・再評価が民主化時代を迎えた韓国社会の中で急速に進んだ。現在、郷里水原には彼女の銅像が立ち、「羅蕙錫通り」が造成されている。生誕百年にあたる2016年には、水原市立アイパーク美術館で「時代の先駆者、出会う」と題された大々的な羅蕙錫展が開かれた。その目録の発刊の辞に、羅蕙錫は「伝統と変化への欲求が吹き荒れた近代の変革期に生まれ、画家として、文学者として、民族運動家として、女性解放論者として自分の思想を実践しながら開拓していく人生を生きた」と紹介されている。
浦川登久恵 (うらかわとくえ)
朝鮮近代文学。熊本大学、熊本学園大学他非常勤講師
著書に『評伝 羅蕙錫』(白帝社)がある



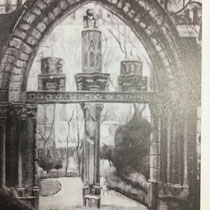



コメントをお書きください